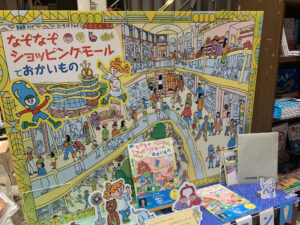「ピサンキ」とは、ウクライナに古くから伝わる、ろうけつ染めで装飾された卵のこと。前回では、陶芸家で、ピサンキ作家でもある飯野夏実さんに「ピサンキ」とはどのようなものなのか、それに描かれた模様の意味について話していただきました。
第2回では、ピサンキはどのように作られるのか、実際につくるところを見せていただきました。

陶芸家・ピサンキ作家、飯野夏実さんインタビュー
ウクライナに伝わる「ピサンキ」って?

陶芸・ピサンキ作家。
神奈川県出身。武蔵野美術大学工業工芸デザイン学科、京都伝統工芸大学陶芸コースを卒業。15歳のときにピサンキと出会い、そこからピサンキの制作を始める。2010年よりクラフトスタジオカラクサを主宰。ピサンキ教室も定期的に開催している。
Instagram ・ Website
ピサンキをつくってみます

どんなふうに、こういうカラフルな色をつけていけるのか教えてもらえますか?

はい。ちょっとやってみましょうか?

ええ、ありがとうございます。
机にコルクマットやタオル、ろうそくなどを準備していく飯野さん。


教室をやるときもこんな感じにセットして、みなさんにやっていただいています。ここにあるのは中身を出してある、からっぽの卵です。まずは下書きをします。何を描きましょうか?

そうですね…では、「春」っぽいのをお願いします。といっても、ピサンキは基本は春を祝うものなんですよね。

基本的にはそうですね。
だいたい、卵のタテとヨコにそれぞれ一周ぐるっと鉛筆で線を描いて、4等分するところからスタートします。


次に「キストカ」という道具を使って線を描きます。シャープペンの先っぽみたいなものに、横向きに軸がついています。ろうそくに火をつけて、キストカをあたためて、ミツロウをすくいとります。

ミツロウを入れられるようになっているんですね。


ミツロウは本来は薄い黄色をしているのですが、描いた線が見えやすいように、黒く色をつけてあるピサンキ用のミツロウをつかっています。


こんな感じで幾何学的に分けていきます。

ミツロウはすぐ乾くんですか?

乾くというか、固まるんですよね。1秒ぐらいしたらさわっても大丈夫。ろうけつ染めというのが、このピサンキのすごく特徴的なところで、絵の具でペイントしているのではないんですね。


本当は卵の全面に絵を描くんですが、それやってると3時間も4時間もかかってしまうので、今日は一部分だけ描いてみます。

あっという間に線が描かれていきますね。

スイスイ線を描けるように見えるんですが、このキストカっていうペンを使いこなせるようにちょっと練習が必要です。

鹿ちゃんを描いてみましょうか。鹿は、ピサンキでは一番よく描かれるモチーフの1つです。


鹿のシルエットがかわいいです。

お花も描きたいですね。鹿の隣の枠にお花を描いてみます。


あっという間にお花が描けました。これだけですごく美しいです。

本当はもっといろいろ描くんですが、今回はこれだけで先進めますね。今度は染料で染めます。染料につける前に、穴※から水が入らないようにミツロウでふさいでいきます。
※卵の中身を取り出すときにあけた穴。


これが染料です。今回は黄色と、赤と、緑を使います。色ごとのタオルも用意してあります。染料は化学染料を使っていて、粉を水にとかしています。
ウクライナの昔の人たちはもちろん化学染料なんかない時代からやっているので、植物染めでピサンキをつくっていたと言われています。玉ねぎの皮で染めたりとか。わたしはアメリカの化学染料でやっています。では入れます。


今かなり思い切ってドボンと入れましたね。割ってしまいそうでドキドキしてしまいます。

卵が浮いてくるので、曲げたスプーンで少し押さえておきます。そうすると、さっきミツロウで描いたところが染料をはじくので、染まらないわけです。いまミツロウが載っているところは、卵の殻の色のまま白く残って、それ以外の場所が真っ黄色になります。

ミツロウで描いていないところが黄色く染まるんですね。

そして取り出します。真っ黄色になりました。染料をタオルで拭き取ります。


そうしたら、今度はまたこの上から模様を描いていきます。そうすると、今から描くところはミツロウでマスキングされるわけなので、最終的に黄色が残るわけなんです。たとえば、この花を黄色にしたいなと思ったら、花の部分をミツロウで塗っちゃうんです。


なるほど。最終的にミツロウをとるってことですか?

そうです。全部取るんです。
最初の大きな割り付けは、下書きをしないときれいに分割できないので鉛筆で描きますが、この描き込みの段階まで行ったら即興的に描いています。小さな点をここに描こうかな、とか。この辺に線を足そうかな、と描き込んでいきます。

その場でその場で描き込んでいくんですか! びっくりです。

次は緑にいれます。さっき塗りつぶしたところは、黄色に染めた段階でロウを置いたので、それ以上染まりません。何も描いていないところが今度は緑色になりました。

色を重ねる順番とかあるんですか?

基本的には薄い順に染めていくんですが、青と赤とかだとどっちが薄いというのはないですよね。青と赤の場合では、後から染める色がちょっと紫っぽく色が混ざってしまうので、赤を鮮やかに染めたいときは赤を先にするとかやっています。大体最初は黄色って感じですね。黒は絶対最後です。
緑に染まったので取り出します。


今度は緑にしたいところにロウを載せていきます。この鹿さんが立っている大地のところを緑にしようかな。鹿さんのまわりに植物を描いて…お花のまわりにも葉っぱを描きます。


こんな感じでいいでしょうか。本当はびっしり埋め尽くすように描きたいのですが、今日は時間の都合上このくらいで。では最後の色に染めます。赤にします。


赤に染まりました。
では、ここからが面白いところで、今度はロウを全部はがしていくんですね。そうすると模様が出てきます。今は真っ黒なので、なんだかよくわかんないですけど。
どうやってはがすかというと、直に火であぶってロウをとかしてふいていきます。あっためれば取れるんです。


火が卵に触れるくらい近づけるんですね。

火であぶって、拭くと…

わーすごい!


こういう感じの模様が出てくる。


すごく鮮やかですね。

今回絵を描いたのは一部だけですが、作り方の流れはこんな感じです。
つくるのがすごく面白い

色を染めるときに、基本薄い色から濃い色にしていくって言ってましたが、赤と緑の順番を変えるとやっぱり変わりますか?

変わりますよ。今日つくったピサンキの場合だと、赤がもうちょっと明るくなって緑がもっと濃い緑になるかな。あと、つける時間にもよります。今回は、緑を濃くしちゃうと次の赤が綺麗に染まらないと思ったので、ちょっと浅めにつけて黄緑っぽくして、赤がちゃんと染まるようにしました。その辺はつける時間とかさじ加減で。

確かに、染料はダークグリーンってありますけど明るい色に染まりましたね。

そうそう、1分ぐらいですぐ出したので。

出てくる色がどうなるかってのも、長年作ってきた経験のつみかさねなんですね。

そうですね。卵にもよるところもあります。
でもやっぱり本当のことは全部はがしてみないとわからないんで、作ってみていまだに、「あれ、ちょっと思ったのと違う」というのも度々あるんですけど笑。


色を染めたくない場所にロウを載せていく感じが、初心者には頭がごっちゃになってしまいますね。

ろうけつ染めは逆転して考えないといけないので、最初はデザインを考えるのがなかなか難しいんですけど、慣れてくると逆転の頭になっているので、最後に卵が真っ黒になっても何が出てくるのかだんだん想像つくようになります。

最後が楽しみですね。卵が染まるってのが面白いです。この限られた画面に世界というか、宇宙を感じますね。

ピサンキは割れたり色も褪せたりするし、手間もかかるので売り物としては難しいのですが、つくるのがすごく面白いので、ピサンキ教室はずっと続けたいなと思ってます。毎月2、3回やっててもう10年くらいやってます。

作るのすごく面白かったです。
(※インタビューに先駆けて、淺田はピサンキ教室に参加していました)

面白いでしょ、つくってみると。

ええ。また教室参加したい!って思いました。今までろうけつ染めの技法のこと、イメージがまったくわかなかったのですが、つくってみてやっとわかりました。
ピサンキの作り方のまとめ
- 準備:卵の中身を空にする
- 卵に鉛筆で下書きをしていく。
- 「キストカ」という道具をろうそくの火であたためて、ミツロウをすくいとる。
- キストカを使って線を描いていく。
- 線が描けたら、染料につけて卵を染める。
- 染まったら染料をタオルで拭き取り、キストカで模様を描いていく。
- 染めたい色数の分だけ(4)〜(6)を繰り返す。
- 模様を描き終えたら卵をろうそくに近づけ、ミツロウを溶かして拭き取る。
できあがり!
絵を卵にミツロウで描き込み、染めて、そして最後にロウをはがしていく瞬間はとてもワクワクしました。
飯野さんは、YouTubeチャンネル「Studio Karakusa」でもピサンキの作り方を動画で紹介しています。ぜひみてみてくださいね。
インタビューの最後の第3回では、どのようにピサンキと出会ったのか、ピサンキをつくり続けながら、陶芸家の道へ進んだ飯野さんのお話をお聞きします。

陶芸家・ピサンキ作家、飯野夏実さんインタビュー
ピサンキとの出会いと、陶芸家として
飯野さんは、台東区の工房「クラフトスタジオカラクサ」で月に2回ピサンキ教室を開催していて、日程の詳細はホームページで確認できます。ピサンキの道具を販売するウェブショップも運営。教室に参加したその日に道具を買って帰ることもできます。
クラフトスタジオカラクサ
https://www.studio-karakusa.com/
ピサンキ材料のお店
https://pysanky.base.shop/
飯野さんの陶芸作品の展覧会情報などはInstagramをご覧ください。